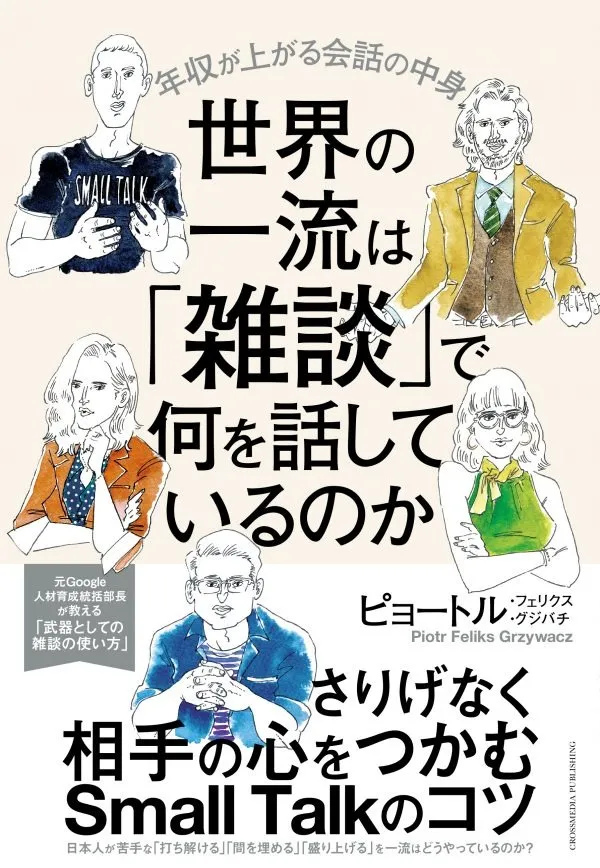組織開発|心理的安全性のために個人ができること
2023/07/28
機能している組織やチームには心理的安全性があり、自分が思っていることを躊躇や忖度することなくメンバーに伝えることができるコミュニケーション風土があります。前回、心理的安全性とはどういうものかをご紹介しましたが、今回はそのために私たちはどんなことをすればいいかをまとめてみました。
メンバー間の相互理解を深める
Googleのように1on1(目的のある対話)をミーティングや面談の場で行うことが多いかと思いますが、その際に3つの目を持つようにします。1つは自分の視点、もう1つは例えば「Aさんはいま私から厳しいフィードバックをするとどう思うだろうか」という相手の視点、さらにもう1つは例えば「私たちは今日の1on1が終わったとき、どんな状態になっているどいいだろうか」という2人を上から俯瞰する視点です。気を付けたいのは、私たちを「You&I」ではなく「We」と捉えることです。私が経営者から依頼されてその企業の部長さんと1つのミッションを実現しようと打合せをするのですが、目指すところは同じのはずなのに、Weではなくどちらかというと敵対されていると感じることがあり、最初の頃はそこの関係構築に時間を費やしたりしました。敵対と感じるときは机を真ん中にして向かい合わせで座っているイメージになりますが、Weの状態は隣に座って同じ方向を向いて目標を目指している様子になります。
発言しやすい環境や雰囲気を醸成する
同じ会社の社員同士として、という前に人として受容し、言葉や態度、行動で示すことが必要です。
<望ましい態度・行動例>
・自分の方から相手の目を見て微笑みながら挨拶をする
・忙しいときに話しかけられても邪険にしない
・ながら作業は一旦止めて相手に身体を向けて話す
・どんなときでも侮辱的な表現を使わない
・反対意見を言われても、不機嫌な対応をしない
未来志向な表現の浸透
「どうせ…」とか「結局は…」とかのネガティブ発言をする人がいる場合、それは可能性に蓋をするだけでなく周りの人のやる気を奪ってしまうため、極力ネガティブ発言は無くしていきたいものです。が、思っていることを言えない場になるのはより心理的安全性を損ないます。よって、愚痴や不満がメンバーから出てきたときは、次に活かす視点を提示するようにします。
<うまくいかなかったときのフォローの言葉例>
・じゃあ、次はこうしてみよう
・もう一度やり方を見直してみよう
・他の方法も試してみよう
・今回の失敗を次へのヒントにしよう
何事も自責で捉え主体的に考えて動く
チームが機能せず前に進んでいる感じがしなかったり、業績が下がったり、結果が出ないなど物事がうまくいかないことが多い変化の時代の中、先述の未来志向は大事であるとともに、「もし私がこうしていたら、どうなっていただろうか?」と考える癖も必要です。自分が思った通りにうまくいかないと人は周りや誰かのせい、会社、社会のせいにしたりして自分を正当化し守ろうとする防衛反応が働きます。「私は悪くない」「私は関係ない」と捉えている限り成長はできません。自分が変わる必要はないと心のどこかで思っているからです。実際に自分が直接関係ないとしても「もし私が…」と考えることができたら、そこから新たな別の行動を取っていくことができます。その姿勢は、自分の周りで起こる出来事は自分の行動次第で何とでもできるという主体的であり、周りとの協働をコミットする行動でもあります。主体的な姿勢というのはコーチングには欠かせない要素であり、もちろん1on1でも必要不可欠なものです。
名古屋や東海3県で社内に1on1の導入やコミュニケーションやコーチングの研修をご検討されている企業さまは無料相談に応じます。お問い合わせフォームからご連絡ください。
---------------------------------------------------------------------
コーチングサプリ
〒466-0002
愛知県名古屋市昭和区吹上町1-10-106
連絡先:https://coaching-suplicom.onerank-cms.com/contact/
----------------------------------------------------------------------